MENU
Home >> �Z�p��� >> ����18�N�x �É����Ƃ̍��k�����ɂ���
>> �É����_�Ɛ��Y���Ƃ̋Z�p���k��
�É����_�Ɛ��Y���Ƃ̋Z�p���k��
- ����18�N�x �É����Ƃ̍��k�����ɂ���
1. �_�ѓy�؍H�����ѕ]���v�̂̉^�p�ɂ���
1) �o���`�y�яo����
| (1) | �l�����ڕʂ́u���Ђ̊Ǘ����ݒ肵�ĊǗ��v�Ƃ��邪�A�Г��K�i���z�����ꍇ�́A��čĎ{�H���Ȃ�������Ȃ��ƕ����܂����B�{�H�Ǘ���̈ʒu�Â��͂ǂ̂悤�ɂȂ�ł��傤���B | |
| �� | �{�H�v�揑�ɏ����ꂽ�u�K�i�l�v�́A���̍H���ł̓K�ۂ肷��K�i�l�ɂȂ�Ƃ����F���ł��B�{�H�v�揑�́u���Ђ̊Ǘ��(�Г��K�i)�v���u�ڕW�l�v�Ȃ̂��u�K�i�l�v�Ȃ̂��A���m�ɂ��Ă��������B ��{�I�ɂ́A���̋K�i�l�œK�ۂ肵�܂��B |
|
2) �u���x�Z�p�v�u�n�ӍH�v�v�u�Љ���v
| (1) | ���x�Z�p�ɂ��ẮA��K�͍H���ɂ����K�p�����ƕ����Ă���B ���K�͍H���̍��x�Z�p�ɂ��ẮA�Y���H�킪�Ȃ��A���Z�_�����Ȃ����ߕs���v�Ǝv���܂��B�H���K�͂ɉ������]�����@�̌��������肢�������B |
|
| (2) | ���x�Z�p�Ȃǂւ̊Y�����ڂ��Ȃ�����ŁA�ǂ̂悤�ɂ�����]�����܂��ł��傤���B | |
| (3) | ���x�Z�p�ɂ����Ď{�H�K�͂̑傫���ւ̑Ή��́A���������Ǝv���B��K�͂ɂ�������]�����1�{�H�����K�̘͂A������H���̂ق������邵�A�H�v��v����Ǝv���B�]���̓��e�����H���̎��Ԃf�������̂ɂ��Ă��炢�����B | |
| (4) | ���x�Z�p��K�v�Ƃ��Ȃ��H����A�����҂̎w���ǂ���ɍs���n�ӍH�v���s�Ȃ��]�n���Ȃ��H���́A�]�����Ⴂ�Ƃ������ʂ��ł�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B | |
| �� (1) �` (4) | ||
| �@ | �u���x�Z�p�v�͎{�H�K�͂̑傫��������Ώۂɂ��Ă���킯�ł͂���܂���B �u���������R�����E�Љ�����ւ̑Ή��v�����]���̑Ώۂł��B �ڍׂ́u�_�ѓy�؍H�����ѕ]���v�́v���Q�Ƃ��Ă��������B �u���x�Z�p�v�u�n�ӍH�v�v�u�Љ���v�ɂ��ẮA���Y�H���̎��{���l�����邱�ƂɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�]�����ė~������g�݂�����Ώ��ʂŒ�o���Ă��������B |
|
| (5) | ���ڕʕ]��_�̍��x�Z�p�E�n�ӍH�v�E�Љ�����_���ڂʼn��_�ƂȂ������e���A�H�����Ƃɒʒm�ł��Ȃ��ł��傤���B | |
| �� | ���ڕʕ]���_�̉��_���ڂ́A�e�ГƎ��ɍH�v�������Ƃ��A�s�[��������̂ł�����A��̓I���e�̒ʒm�E���\�͍l���Ă��܂���B�]�������́u�_�ѓy�؍H�����ѕ]���v�́v�Ɏ����Ă��܂��̂ŎQ�l�ɂ��Ă��������B | |
| (6) | �n�ӍH�v�ɂ����ĉߋ��ɑ�����ɂ����Ď��{�������ƂƓ��l�ȓ��e�ƂȂ�ꍇ�����邪�A�]���͂���Ȃ��̂ł��傤���B�܂��A�n�ӍH�v�������펯������A���������{���Ȃ��ꍇ�͉��_�[���A�������͌��_���ڂƂȂ�悤�Ȃ��Ƃ�����̂ł��傤���B | |
| �� | �������e�ł������Əꏊ���i�P�[�X��o�C��P�[�X�j�ɂ��]�����s���܂��B �܂��A�u�n�ӍH�v�v�͉��_���ڂŁA���_����邱�Ƃ͂���܂���B �y���Ȃ��̂ŁA�Ƒn���ɕx�݁A���M���ׂ����ʂ̂������H�v�͕]�����܂��B |
|
| (7) | �Љ���ɂ����ĎR���H���s�X�n���痣�ꂽ�ꏊ�ł̍H���A�܂��͏��z�H�����Œn��ւ̍v���ȂǏ��Ȃ�����ł͕]���_���Ⴍ�A�s�����̂悤�ȋC�����܂��B | |
| �� | �{�H����H��(�������)�̒��Ōy���Ȃ��Ƃł��A�n��Љ��Z���ɑ��z���E�v���ł��邱�ƂɎ�g��ł��������B����Ƃ��s�����������Ȃ��悤�]�����ׂ��͕]�����܂��B | |
| (8) | �n��v�����œ��e���G�X�J���[�g����X���ɂ���B���Ƃ��A������ӂ̐��|�������͂�����܂��ŁA�\����E���ӏ��Ȃ���ΔF�߂Ă��炦�Ȃ��A�Ƃ��������������܂��B���܂�̉ߑ�v���͂Ȃ��悤�ɂ��Ă������������B | |
| �� | �u�Љ���i�Љ�v���j�v�͍H���̎{�H�ɔ����āA�n��Љ��Z���ɑ���z�����̍v���ɂ��ĉ��_�]��������̂ł��B��̓I�ɂ́A������ӂł̊��ۑS�A�n��̃{�����e�B�A�������̎�g�݂ł���A�ߑ�ȍv����v��������̂ł͂���܂���B �Ȃ��A�Љ�v�����e�ɂ��ẮA���O�Ɏ{�H�v�揑�ɖ��L���Ă��������B |
|
3) ���̑�
| (1) | �{�H�v�揑�y�яo���`�Ǘ��ɂ��ẮA���ނ̖����������قǐ��ѕ]�����オ��A�Ƃ̂��Ƃ̂悤�ł����A���ނ̊ȑf���ɋt�s���Ă���悤�Ɏv���܂��B | |
| �� | ���ނ̖����������قǐ��ѕ]�����オ�邱�Ƃ͂���܂���B�{�H�v�揑�́A�H���̊T�v�A�{�H�̃|�C���g�A�{�H���j���̕K�v��������R�Ȃ��Ȍ��ɋL�q����Ă���v�揑�A�܂��o���`�Ǘ��́A�Ǘ���������₷���Ǘ��\�E�Ǘ��}��]�����܂��B | |
2. �d�l�����̉^�p�ɂ���
| (1) | �{�H�v�揑�쐬���@�́A�������z�ŋL�ړ��e����������Ă��܂����A����ȏ�̓��e��v������邱�Ƃ�����܂��B�d�l���ɂ������쐬���@�̓����}���Ă������������B | |
| �� | �u�_�ѓy�؍H�����ʎd�l���v�ł́u���K�͍H�������戵�v�̂ɂ��L�ړ��e�̈ꕔ���ȗ����邱�Ƃ��ł���v���ƂɂȂ��Ă��܂��B�܂��u�ē����w�����������ɂ��ẮA�����҂́A����ɏڍׂȎ{�H�v�揑���o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v���Ƃɂ��Ȃ��Ă��܂��B�w�������ɂ��ẮA�ē��Ƒō��������Ă��������B | |
| (2) | ���ނ̍쐬���@���ē��ɂ���ĈقȂ�ꍇ������B | |
| �E | �ł��邾�����ꂵ���X�^�C���ɂ��Ă������������B | |
| �� | �u��������̎�����v�ɂ́u�{�H�v�揑�̍쐬��v������܂��������܂ŎQ�l�ł������҂̓p�^�[�����������̂ł͂Ȃ��A�d�l�������߂鏊��̍��ڂɂ��āu�_������ƌ�������f���A�ǂ��ړI���ɂ��邽�߂ɏ[�����������{�H�v�揑�v���쐬���Ă��������B | |
| (3) | �i�K�m�F�̎��{�p�x���A�d�l���Œ�߂��Ă���ȏ�ɑ����v�������ꍇ������B | |
| �E | �d�l���Ɋ�Â����Ǘ��Ƃ��Ă������������B | |
| �� | �u�ēv�́v�ɂ͊ē��̈�ʓI�ȊēƖ��̕W����������Ă��܂����A�H�����e���ɂ�肱�̕W���i��j�ɂ��Ȃ��ꍇ���F�߂Ă��܂��B�i���m�ۂ̂��߁A�i�K�m�F�͏d�v�ȊēƖ����Ɨ������Ă��܂��̂ŁA�ǂ��H�����ʂ邽�ߐ����ҁE�ē������͂��邱�Ƃ��K�v�ƍl���܂��B�ē��Ƒō��������Ă��������B | |
3. �v�E�v�ύX�ɂ���
1) �����v�ɂ���
| (1) | ���{�H�ɂ������ώZ�����Ă������������B�i�g�p�@�B�A���݁A�H�����j | |
| �� | �e�H���́A�W���I�Ȏ{�H�Ɋ�Â��A�ώZ���Ă��܂����A�ł�����茻��ɑ��������e�ƂȂ�悤�w�����܂��B | |
| (2) | ���H�H�̐}�ʋL�q��mm�P�ʂł���A�}�s�Ȓn�`��mm�P�ʂ̊Ǘ��͍���ł���B | |
| �� | �\�����̊Ǘ��l�͋��ʖ��͓��L�d�l���Œ�߂�悤�ē��Ɏw�����Ă��܂��B �������A�s���m�ȏꍇ�͊ē��Ƌ��c�̏�A���߂Ă��������B |
|
| (3) | ���n�����ނ̎g�p�ɂ��āA�g�p�ł��Ȃ��ޗ��̏����ꏊ�A���@���m�ɂ��Ă������������B | |
| �� | �Y�p�i���n�����ށj�̏�����p�̌v��A�����ӏ��E���@�͓��L�d�l���ɋL�ڂ���悤�w�����܂����A�����A����Ŕ��������ޗ��͎Y�Ɣp�������Ǝғ��֓K���ɏ������Ă��������B | |
| (4) | �y�H���ɂ����āA�ؓy�@�ʌ��z������3���A�����y�E�I���y�ł�6���ƋK�肳��Ă���B�ؓy�����̐ݒu�͊�Ցz�������ɐݒu�����邪�A����̃��C���Ɋ�Ղ������ꍇ�A�ēx��n�߂���C�����s���̂ŁA���S�ʂ�����댯�ł���B | |
| �E | �ؓy���z��6���Ƃ��A��₪�o�������珬�i��݂�3���Ő؎��悤�ɂ͏o���܂���ł��傤���B | |
| �� | ���O�����̏�A�v�ώZ��K�ɍs�������{�݂̎{�H�͈́i�p�n�A�����ʐϓ��j�����߂Ă��܂����A�W�L�̂悤�Ɉ��S�{�H�̖ʂ���v�ύX���K�v�ȏꍇ�͑��₩�ɋ��c�����o���ċ��c���Ă��������B | |
| (5) | �����}�ʂƌ��n�Ƃ̑���_���ŋߖڗ��悤�Ɏv���܂��B�����O�Ɋm�F�����肢�������B�����}�ʂ̏��������������悤�ɂ������܂��B | |
| �� | ���̂悤�ȃP�[�X���������ꍇ�A�����ґ��̐ӂŐv�}�����C�����܂��̂Łu�v�}���̏ƍ��K�C�h���C���v�ɏ]���Ċē��Ƌ��c���A�w�����Ă��������B | |
| (6) | ���ꂩ�甭�����鍪���̏����ɂ��Ăǂ̂悤�ȍl�����A�������肢�܂��B | |
| �� | �H�앨�̐V�z�A���z�܂��͏����ɂ���Đ��������́A�����ނ͎Y�Ɣp�����ł��B �����Ǝ҂���������ӔC���Ă���A�Y�Ɣp�����̋��Ǝ҂ɏ����ϑ����邱�Ƃ��K�v�ł��B�Ȃ��A����珈����͔����ґ����v�シ�邱�ƂƂȂ��Ă��܂��B |
|
2) �v�ƍ��ɂ���
| (1) | �v�ƍ��̋L�^�l�����Ȃ��̂Ŏ����Ă������������B | |
| �� | �������܂��B | |
| (2) | �v�ƍ���̔����ҁA�R���T���A�҂ɂ��H���ė��A����͕K�����{���Ă������������B | |
| �� | �d�v�\�����̎{�H���ɂ͍s���悤�w�����Ă��܂����A�҂���̗v�]���{�H�v�揑�쐬���A�{�H�����܂ߐϋɓI��3�Ғ��������{����悤�O�ꂵ�܂��B | |
| (3) | �v�ƍ����{�ɂ�����A�R���T���Ɛ����҂̐ӔC�͈͂���薾�m�ɂ��Ă������������B�����҂͈̔͂���������Ǝv���܂��B | |
| �� | �H����i�߂�ɂ�����A��Ɨʂ̕��ӔC���S���s���m�ɂȂ��Ă���Ƃ̐������ɂ��܌����H����i�߂��ŁA�e�����̐ӔC�m�ɂ��A��Ƃ̕肪�����Ȃ��悤�w�͂��܂��B | |
3) �v�ύX�ɂ���
| (1) | �H���̕ύX�͔����҂Ǝҋ��c�̏�ł��肢�������B | |
| �� | �H�������̍ۂ́A�K���ȍH����ݒ肵�_��������Ă��܂��B �H���́A�H�앨�̃R�X�g�ƕi�����m�ۂ����ŏd�v�ȗv�f�ƍl���Ă��܂��B �������A��ނ��H���ɕύX��������ꍇ�͑o�������c���邱�ƂƂȂ��Ă��܂��B�o���̍��Ӗ����ɍH�������_�s���Ȃ��悤�w���O�ꂵ�Ă����܂��B |
|
| (2) | �ύX�_��ŋ��z�͑��z�݂̂̒ŏڍׂ��s���ł���A���������Ɏx������B | |
| �� | ���� | |
| �� | �w�����␔�ʕ\�ŕύX���e�̊m�F�����Ă������������B�K�v������A�ύX�̒P�����v�����ē�������炤�悤�ɂ��Ă��������B | |
| (3) | �ύX�w����K�X���{���Ă������������B�O���A�������l�͂̏��ޒ�o�Ɏx�Ⴊ�ł�B | |
| �� | �ύX�w���́A���₩�ɕύX�w�������o���悤�O�ꂵ�܂��B | |
| (4) | ���J�E�����͒n���҂ɕ⏞��Ƃ��Ďx�����Ă���Ƃ̂��Ƃł��������A����͎{�H�҂��s���Ă���B��p�������H�̒��ɔ[�܂�Ȃ����̂ق��������B | |
| �E | �n���҂ɕ⏞����i���J�E�����j���ς܂��āA�H������ƂȂ�l�w�����Ă������������B | |
| �E | �����H�̔��J�A�����̔�p�����Ă������������B | |
| �� | �ŋ߂ł͒n���҂ɂ�鏈��������ƂȂ��Ă��邽�߁A�{�H�҂ɍ�Ƃ����肢����H���������Ȃ��Ă��܂��B���łͤ��������(�������̐ӂɂ�蔰��)�̏ꍇ�́A�a5�p�ȏ�̗���ΏۂɍH����̒��Ŕ��́E�W�ρE���o�^���E��������v�サ�܂��B | |
| (5) | �H�Չ��ǂɂ����āA�v�̍H�@�łȂ����̍H�@���Ă��܂������A���H���H���ł͒�čޗ��͎g�p���Ă��Ȃ�����A�Ƃ������ƂŌ������Ă��������܂���ł����B �O�����Ȍ��������肢�������B |
|
| �� | �{�H���A�o�ϐ��y�шێ��Ǘ��ʂ𑍍��I�Ɍ������A�L���ȍޗ��E�H�@�ł���ΐϋɓI�Ɏg�p���Ă����̂ŁAVE��ē���ϋɓI�Ɋ��p���Ă��������B | |
| (6) | �v�ύX�Ɍv������肢�������B | |
| �E | �c�y�����͌���̏ɉ��������̂Ōv������肢�������B �i4,000m3�̓y�������͂ɎU�炷�v�ł��������A�_���v�^���ŏ������s�����j |
|
| �� | ���ݕ��Y���̏����͓K���ɍs���悤�w�����Ă���Ƃ���ł����A����W�L�̎��Ⴊ�������Ȃ��悤�ē��ɍēx���m���܂��B | |
| �E | �v�y���^�������͐����ł��邪�A�}�s�Ȓn�`�ł���^��������2�{�ƂȂ����B �ύX�ΏۂƂȂ�Ȃ��̂ł��傤���B |
|
| �� | ���ʐ}�ʼn^���������v�����v����ꍇ���������A����ɂ�����Ȃ��ꍇ�͊ē��Ƌ��c���Ă��������B | |
| �E | ���S�ʂ�艼�݂��������āA���މ^���������ɂ��s�������A���������ƂȂ�����Ɠw�͂ŏ���������Ȃ��ꍇ������A�����肢�����B | |
| �� | �����ŋ��c���A�K�v�Ȃ��͎̂咣���ė~�����B | |
4. �H���Ǘ��ɂ���
| (1) | �T�������ł��邽�ߕύX�������������c������o��̗ʂ����Ȃ葽���Ȃ����B ���f���ʁi�v�}�ʁj�͔����҂��s�Ȃ��ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤���B |
|
| �E | �v�͂ł��邾���ו��܂ōs�Ȃ��Ă��������A���������Ă������������B | |
| �E | �H�����肪���₩�ɂł��A�{�H���~���ɐi�߂���ƍl���܂��B | |
| �E | �H������O�ɒ������ʓ������ނƁA�o��̏o������čH���������������܂��B | |
| �� | �{�N�x����T�Z�i�T���j�����͎��{���Ă��܂��A����ɓO�ꂵ�܂��B �����ɍۂ��A�É������ݍH�������_���18���ɒ�߂錻��������ȊO�̕ύX�������Ȃ��悤�w�͂��Ă��܂��B |
|
| (2) | �u�i�K�m�F�E�����v�u�x���E��ԍ�Ɠ́v���̏��ނ́A���[���ł̑Ή��ɂȂ�Ȃ��ł��傤���B�{���͌����o���܂��B | |
| �� | �d�q�[�i�쐬�̎b�菈�u�Ƃ��āu�ō����듙�v�̃��[�����p��F�߂Ă��܂��B �ē��Ƒō��������Ă��������B ���[�����p�@�F�u�i�K�m�F�E�����v�u�x����ԍ�Ɠ́v���̓��[���ɂđ���M���s�����e�̊m�F������B����A�����҂́u���M���[���v�ɉ���B |
|
| (3) | �����}�ʂɂ����āA����E�����E�p�x���̐��x�������ɂ�������炸�A�����҂ɂ͕K�v�ȏ�̐��x�̗v��������܂��B | |
| �� | �����}�ʂ̐��m���ɗ��ӂ���悤���ȏ�Ɏw�����Ă����܂��B | |
| (4) | �אڍH��̕ύX�ɂ�錸�z�Y�H���ɒlj��ƂȂ�A�H���E�\�Z�ɖ����������A���S�Ǘ��E�i���Ǘ����ɂ�������܂��B | |
| �� | ��������z�̕ύX�ɂ��Ă͗��ҋ��c���Ē�߂邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B �ύX���c�́A���S�Ǘ��A�i���Ǘ����A����������ēx�������A�ē��ƍs���Ă��������B |
|
| (5) | ���ނɏd�_�������X���ɂ���A��o���鏑�ނ������Ă��܂��B����ł͐F�X�ȉۑ肪�������A�����ɑΏ����邱�Ƃ����S�ƂȂ�A���ޑΉ��͎c�ƂɂȂ�܂��B ���ނ̊ȑf���i�K�v���̌������j����w�}��悤���肢���܂��B |
|
| �� | ��o���ނ������Č��ꂪ��ς��ƌ����ӌ��͏��m���Ă��܂��B����Ƃ��ȑf����}��w�͂����܂����A�K�v���ɋ^�₪����ꍇ�͊ē��Ƒō��������Ă��������B | |
5. �H���Ǘ��Ɩ��̎��Ԃɂ���
| (1) | �����͌���Ǘ�����̂ƂȂ�A�ώG�����剻���Ă��鏑�ނ̍쐬�͎c�Ƃ��邢�͋x���o�őΉ�������Ȃ��B���ł��ύX���ފW�̍쐬�ɑ����̎��Ԃ���₳��Ă���Ǝv���܂��B ���X�̎c�Ƃɂ��Ă͕K�v�ȕ����ł���ƔF���͂��Ă���܂����A�x���ɂ��Ă͌���̏������A�V��A���ލ쐬�����d�Ȃ�܂��̂ŏ���̓������m�ۂł��Ă��Ȃ��̂�����ł���܂��B |
|
| �� | �����H���́A���i���B�Ƃ͊�{�I�ɈقȂ�A���̕i���͖ړI�����g�p����ď��߂Ċm�F�ł�����̂ł��邱�ƁA�����҂̋Z�p�I�\�͂ɂ���ĕi�������E����邱�Ɠ��܂��A�����H���̕i���m�ۂɊւ����{���O���߁A�����҂̐Ӗ��m�����鏔�K��̐�����ړI�Ƃ��Ģ�����H���̕i���m�ۂ̑��i�Ɋւ���@���������17�N4��1���{�s����܂����B�܂�����17�N8��26���ɂ́A���̖@���̊�{�I�ȕ��j���t�c���肳��܂����B���̂悤�Ɍ����H���ł͔����҂ɑ��āA���܂łɂ������Č����i�[�Ŏҁj�ɐ����ӔC�����߂��Ă��܂��B���������̂��߁A�҂ɖړI�����d�l�ǂ���ɓK���ɍ\�z����Ă��邱�Ƃ̏ؖ����K�v�ƂȂ��Ă��Ă��܂��B ���̏ؖ��̕��@�Ƃ��āA�]�O�̂悤�Ȏ����ނ������Ȃ��Ă���̂������ł��B �����ނ��ŏ����ɂ���悤�ɁA��o�̕K�v���Ȃ����̂́A�i���������ɐ��{�̊m�F�j�ōς܂���悤�ɂ��Ă��܂��B �Ȃ��A���K�́A���z�H���ł́A��o���ނ̊ȑf����}���Ă��܂��B |
|
6. ���̑�
1) �d�q�[�i
| (1) | �������Ƀp�\�R����ʂł͌������s�����Ƃ�����ȏꍇ�������A�v�����g�A�E�g�������̂��o����悤�w�����ꂽ�B �d�q�[�i���ނƌ����p���ނ̓�d�Ǘ��ƂȂ邱�Ƃ̂Ȃ��悤�ɁA�d�q�}�̂���ю��x�[�X�ł̍쐬�͈͂m�ɂ��Ă������������B |
|
| �� | �d�q�[�i�Ώۏ��ނ̌��蓙�ɂ��Ắu�d�q�[�i�^�p�K�C�h���C���i�āj�v�Œ�߂Ă���Ƃ���A�_���̔����҂Ǝ҂̋��c�ɂ�茈�肷�邱�ƂƂ��Ă��܂��̂ŁA�����҂Ə\���ȋ��c���s���悤�ɂ��肢���܂��B�^�p���j�m�������c���~�������邽�߁A�d�q�[�i�̑Ώۏ��ނ⌟���̎��{���@���ɂ��āu�É����d�q�[�i�쐬���j�v���߁A�H���������z�[���y�[�W�ɂČ��J���Ă��܂��B �u�d�q�[�i�쐬���j�v�ł́A�����Ƃ��ďo���^�Ǘ���i���Ǘ����ނ͓d�q�̕K�v���Ȃ��A�{�H�v�揑��H���ō����듙�̃I���W�i���f�[�^������ꍇ��CD�֊i�[����ƒ�߂Ă��܂��B�����̕��j�ɂ��ẮA�p�\�R���ł͎ʐ^�݂̂��������A���̏��ނ͎��Ō������邱�Ƃ������Ƃ��Ă��܂��B �d�q�[�i�ΏۍH���̏ꍇ�̓p�\�R���ł��ׂČ�������悤�ɂ��Ă��܂��B |
|
| (2) | �����}�iCAD�f�[�^�j�ɂ��Ă͍ו��ɂ킽��܂Ō��ߎ�������܂��B������x���R�ȑI�����������Ă��ǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����ł͐}�ʍ쐬�Ɏ��ԂƔ�p�������肷���܂��B | |
| �� | �ē��ƒ���O�ɋ��c���ė~�����B�d�q�[�i�ł͐}�ʃf�[�^�̕W������}��ړI�Ƃ��āACAD���}������肵�Ă���A�}�ʃf�[�^�����t�H�[�}�b�g��SXF�`���ƒ�߂��Ă��܂��B����ɂ��A���ꂵ��SXF�`���ł̃f�[�^�������W�ҊԂʼn\�ƂȂ�܂��̂ŁA�ׂ���������߂Ă��܂��B �d�q�[�iCAD���}��Ō��߂��Ă��܂��̂ŏ������Ăق������A�`�F�b�N�V�X�e���ŃG���[���o�Ȃ��͈͂ʼn��ǂł��܂��B |
|
| (3) | ���ޓd�q���͈̔͂̋��c�ɂ����Ĕ����ҁA�҂��݂��ɗ���s��������悤�Ɏv���܂��B���O�̋��c���ł���@��������Ă������������B | |
| �� | ����O�ɒ�o���e���ɂ��ċ��c���邱�ƂƂȂ��Ă��܂��B ���O���c�́A�������@��Ώۏ��ށA���ނ̎戵�����̐��ʕi�̓��e��\�ߌ��߂āA�H�����Ԓ��̍�����h�����߂ɍs�Ȃ��܂��B���̂��߁A�K���_���Ɏ��O���c���s���A���c���ʂɂ��Ă͏��ʂɎc���Ă��������B |
|
| �E | �����ґ��Ɛ����ґ��Ƃœd�q�[�i�ɑ�����i�n�[�h�E�\�t�g�ʁj���قȂ�A�܂��̓o�[�W�������̍�������܂��B | |
| �� | ���O���c�̎��_�œd�q�[�i�����`�F�b�N�V�[�g�i�H���E�ϑ����ʁj�ł��݂��Ɋm�F���Ă��������B | |
2) ISO���p�H��
| (1) | ISO���p�H���̎��тƍ���̎戵�����j�������Ă������������B | |
| �� | ���y�ؕ��ł́A����13�N�`16�N�x�Ԃ�ISO���p�H���̎��s���s���܂����B���̌��ʁA���p�H���ȊO�̍H�����тƑ卷���Ȃ����ƁAISO9001�̔F���擾���Ă���Ǝ҂�A�AB�Ǝ҂��唼���߂Ă��邱�Ƃ���A���D�����Ƃ��Ĉ���Ȃ����Ƃɂ��܂����B�_�Ɛ��Y���A���X�ѕ��ł����l�̈��������Ă��܂��B ����17�N�x�i6��1���ȍ~�j����́A500���~�ȏ�̍H���ɂ��ė��D�����Ǝ҂̐\�����iISO9001�F�؎擾�����p�����ēƖ��j�Ƃ��A�O�N�x�A�O�X�N�x�̍H�����ѕ]�蕽�ϓ_��75�_�ȏォ��64�_�ȉ��̍H�����Ȃ����Ƃ������ɏ��F���邱�ƂŎ��{���Ă��܂��B ���̋Ɩ��̃����b�g�͒i�K�m�F�̉����炷���Ƃɂ���A���Ɍ��ꂪ���������牓���ꍇ�ɂ́A�S���ē��͋Ɩ��̌��������}��A�����҂͒i�K�m�F�҂��̎��Ԃ��Z�k����邱�ƂōH���̒Z�k��}�邱�Ƃ��ł��܂��B ����A���ƊE�ɂ͈�w�̎�g�݂����҂���Ƃ���ł��B |
|
3) VE���x
| (1) | VE��Ă������v��ے肷��悤�ȈӖ������ɂȂ�ꍇ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�܂�VE��Ă��P�Ȃ�v�ύX�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ�����悤�ł��B VE��Ă����āA���C�t�T�C�N���R�X�g�̒ጸ�ɍv�������Ǝ҂Ƀ����b�g�̂��鐧�x�Ƃ��Đ��i�����Ă����Ă������������B |
|
| (2) | VE��Ă����āA�̗p�s�̗p������Ǝv���܂����A���̊�Ȃǂ�����������肢�܂��B | |
| �E | ��Ă����c�ɂčs�����Ƃ�����A���v��ς��Ă��܂��ƌ�ɖ�肪���邩��Ƃ������ƂŁA���ۂ��ꂽ�P�[�X������܂����B | |
| �� | VE��Ă͍H���̖ړI���̋@�\�A���\����ቺ�����邱�ƂȂ��A�H�����ጸ�����邽�߂̍ޗ��A�{�H���@���̕ύX��Ăł��B VE��Ă̐R���ł́A�{�H�̊m�����A���S���A�o�ϐ������߂��A���̕ύX�� �����H��������H���ړI���̕ύX��Ȃ����Ƃ����߂��܂��B �H���{�H�ɐ��ʂ����F����̍l����ϋɓI�ɒ�Ă��Ă��������B |
|
| (3) | �ߋ���VE��Ă̎��т͂ǂ̂悤�ɂȂ��Ă���܂����B�܂�����̎�g�݂̕��j�͂ǂ̂悤�ɂȂ��Ă��邩�������肢�܂��B | |
| �� | �ϋɓI�Ɏ��g�ݒ��Ă��������B �ߋ��̎��т́A�_�n1���iH13) �X�тP���iH17�j�ł��B |
|
4) ���D���@�i�����]���A���\�K�蓙�X�j
| (1) | �]����Ɂu�ߋ�10�N�Ԃ̎�C�Z�p�҂Ƃ��Ă̎{�H�o���v�Ƃ��邪�A�����Z�p�҂����Y�����܂���B����㗝�l�܂��͒S���Z�p�҂Ƃ��Ă̎{�H���т��]���ΏۂƂ��Ă������������B | |
| �� | �����H���̋Z�p�Ǘ��́A�ړI���̎{�H�Ɋւ���Z�p��o����L�����C�Z�p�҂��풓���A����Ǘ��ɂ�����Z�p��̊Ǘ����s�Ȃ����ƂƂȂ��Ă��܂��B �������A���Ɩ@�ł́u����㗝�l�͐����_��̓I�m�ȗ��s���m�ۂ��邽�߁A����̎����A�����������A�����l�̑㗝�Ɩ����s���v�Ƃ��Ă���B ����Č��ݍH���̓K���Ȏ{�H���m�ۂ��邽�߂ɂ́A��C�Z�p�҂̋Z�p�A���т݂̂�]���ΏۂƂ��Ă��܂��B |
|
| (2) | �����]���̕]���_���̂����������Ă������������B�܂��H���K�͂ɂ��Ⴂ������̂ł��傤���B | |
| (3) | �����]���̋Z�p�����쐬��o�܂ł̎��Ԃ����Ȃ��B �ȈՂȎ{�H�v�揑�쐬�ɂ����Ă��A���n�m�F�E�������K�v�ŁA�����쐬�Ɏ��Ԃ��K�v�ƂȂ�܂��B�쐬���Ԃ̗]�T���������Ă������������B |
|
| �� | �_�Ɛ��Y������������H���ɂ��Ă͌��������ł��B ����19�N4�����瑍���]�������ɂ����D�����s�\�肵�Ă��܂����A���ʂ͊ȈՂȎ{�H�v�揑�̒�o��q�A�����O���A��Ƃ̋Z�p�͂�]������ȈՌ^�݂̂ƂȂ�܂��B |
|
| (4) | �Z�p�����ɂ����āA�w�肳�ꂽ�{�H���@�ł͍H���������������ł���Ɣ��f�����ꍇ�A�x���H���̒�o�͉\�ł��傤���B�܂��A�{�H���@��ς��č쐬���������̒�o�͉\�ł��傤���B | |
| �� | �������ꂽ�H���́A�v�E�{�H�E�H�����̏����ŗ��҂��_�Ă��邽�߁A�O�I�v���i�v�}���ƌ�������̕s��v�Ȃǁj�ɂ����̈ȊO�A�_��ɔ����鋦�c�͎��܂���B �Ȃ��AVE��Ăɂ��A�R�X�g�A�H�����̉��P���}���ꍇ�͂��̌���ł͂���܂���B |
|
5) ���j�b�g�v���C�X����
| (1) | �ώZ���@�́A���ڍH����ɁA���ʉ��݁A����Ǘ���𗦌v�サ�ĒP���ɍ��킹�A���j�b�g�P���Ƃ���B���Ƃ͈�ʊǗ���(���o��)���v�シ��Ɖ��߂��Ă���܂��B ���݂̎�g�ƍ���̑Ή��E���j�ɂ��Ă������肢�܂��B |
|
| �� | �_�ѓy�؍H���͌��������ł��B ���ۉ^�p���邽�߂ɂ͒~�σf�[�^�������K�v�̂��߁A���ʂ̊Ԃ͎��{���܂���B |
|
6) ���T�C�N���@
| (1) | ���T�C�N���@��o���ނ̍쐬�ŁA�ʕ\�R�u���ʉ�̓��̌v�擙�v�̔p�������������ݗʂ̋L�ڂɂ�����A�����ݗʂ̎Z�o���@�ɂ��ċ����Ă������������B | |
| �� | ���݃��T�C�N����o���ނ̗���ƐӔC���S�͉��}�̂Ƃ���ł��B �u���ʉ�̓��̌v�擙�v�́A�����Ǝ҂������҂ɑ����ʂŐ������A�����҂����m���֍H������7���O�܂łɓ͏o���邱�ƂƂȂ��Ă��܂��B ���ނ̋L�����@�A���e�ɂ��Ă͔����҂ƒ����̂�����o���Ă��������B |
|
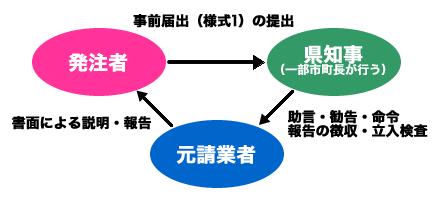 |
||
7) �v�]�����A��ē�
| (1) | ������̂ƂȂ���ǂ����̂����グ�邱�Ƃ��ۂ���ꂽ�e�[�}�ł��邪�A�����ҁE�҂����݂��ɗ����������A���͂������Đi�߂Ă������Ƃ�����ƍl���Ă���܂��B | |
| �� | �����ł��B | |
